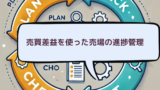「売買差益」と「荒利(粗利)」の違い
小売業において、売上の数字を見るだけでは、儲かっているのかわかりにくいことが多いです。例えば通常より安値で売っているので売上が増えるけど、利益がでていないなど目玉商品ではよくあるケースです。その為、利益もしっかり みておきたいのですが、荒利(粗利「以下、荒利」)を把握するのは面倒なことが多いため「売買差益」が用いられます。今回は売れている+儲かっていいるを見るための数値に使われる「売買差益」と「荒利」の違いをまとめました。
みておきたいのですが、荒利(粗利「以下、荒利」)を把握するのは面倒なことが多いため「売買差益」が用いられます。今回は売れている+儲かっていいるを見るための数値に使われる「売買差益」と「荒利」の違いをまとめました。
売買差益とは?
売買差益とは、売上高と仕入高の累計差を示す指標で、日々の利益状況を簡易的に把握するために使用されます。この概念は、荒利とは違い棚卸在庫を加味せず、日々の売上と仕入をもとに計算されます。
・売買差益の計算式
売買差益=売上高-仕入原価
粗利益とは
一方、粗利益は、売上高から売上原価を差し引いたものです。ここで「売上原価」には、仕入れた商品の原価だけでなく、期首在庫と期末在庫の変動も加味されます。粗利益は、ロスや売価変更など収益力を判断するために使われ、月次や年次の損益計算において重要です。
・荒利の計算式
荒利=売上高ー売上原価(※)
(※)売上原価=期首原価在庫高+期中仕入原価-期末原価在庫高
計算の違いは、黄色のマーカーのところです。荒利は、期首原価在庫がプラスされ、期末原価在庫がマイナスされています。これだけの違いなのですが、小売業で期末原価在庫高(翌期の期首原価在庫高)を確定することは”棚卸”をしないとわからないので、正確な数値把握がとても面倒なのです。その為、売買差益は利益判断するために日次や一定期間の管理などで実務上利用します。
売場の部門別に売上のデータPOSから持ってこれるので、どの部門が利益がでているのかなど、予算比較などに利用できます。荒利が計算されるのを待って売場を変えて行くのでは間に合わないのです。さらに期首在庫プラスし、期末在庫をマイナスしても売場に在庫数が一定であれば、荒利をもとめてもあまり差が出ないので使われています。
逆に、荒利は、期間で区切って数値を出さなくてはなりませんが、売価変更高(売変)、ロス高(帳簿在庫高と実在庫高の差)などを分析しロスの原因分析、削減策、売変などの有効性を検証するなど店舗運営を見直していくために利用することができます。ロスが多くなるのはお店の管理レベルのバロメーターと言われています。ロスをなくす取り組みなど時間もかかるしテーマを作って施策をきめることもありますので荒利で判断するのに向いています。
簿記の勉強をされた方にとっては、売買差益はとても違和感があり、「仕入原価だけでは正確な数字にならない」と疑問に思う方もいますが、小売の在庫高は期首と期末であまり変化がないので結構使える数字なのです。
計算事例(数値を使って把握する)
| 項目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 売上高 | 20,300 |
| 期首在庫高(原価) | 1,358 |
| 期中仕入(原価) | 16,900 |
| 期末原価在庫(原価) | 1,340 |
| 売変高 | 600 |
部門Aの売上高、期首在庫高(原価)、期中仕入(原価)、期末原価在庫(原価)、売変高が上記の表のようにあった場合、荒利率と売買差益率はどうなるか計算してみましょう。
(粗利率)
売上原価=期首在庫高(原価)+期中仕入(原価)-期末原価在庫(原価)
=1,358+16,900-1,340
=16,918
荒利高=売上高-売価変更高-売上原価
=20,300-600-16,918
=2,782
粗利率(%)=荒利÷売上高×100
=2,782÷20,300
=13.7%
(売買差益率)
売買差益=売上高-期中仕入(原価)
=20,300-16,900
=3,400
売買差益率(%)=売買差益÷売上高×100
=3,400÷20,300
=16.75%
数値を活用した運営改善のヒント
例で計算すると売買差益率と荒利率に約3%の差が出てしまいましたね。これは売価変更額が関係しているようです。売価変更の内容がどのようなものであったのか検討することで、オペレーションが改善されていくことが期待されます。売価変更がまずいのではなく、なぜ売価変更をしないといけなかった理由が、頭を使うポイントだと思います。例えば、商品が売価変更しないといけない商品であった場合、タイムセールを頻繁におこなったのではは意味合いが異なりますし、どちらもほったらかしにはできないですね。
売買差益と荒利の計算をしっかりと理解することで、日々の利益判断や店舗運営の改善に役立てることができます。在庫管理や販売戦略の見直しに直結する重要なポイントです。この記事を参考に、自社のオペレーション改善に役立ててみてください!